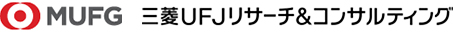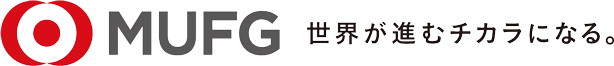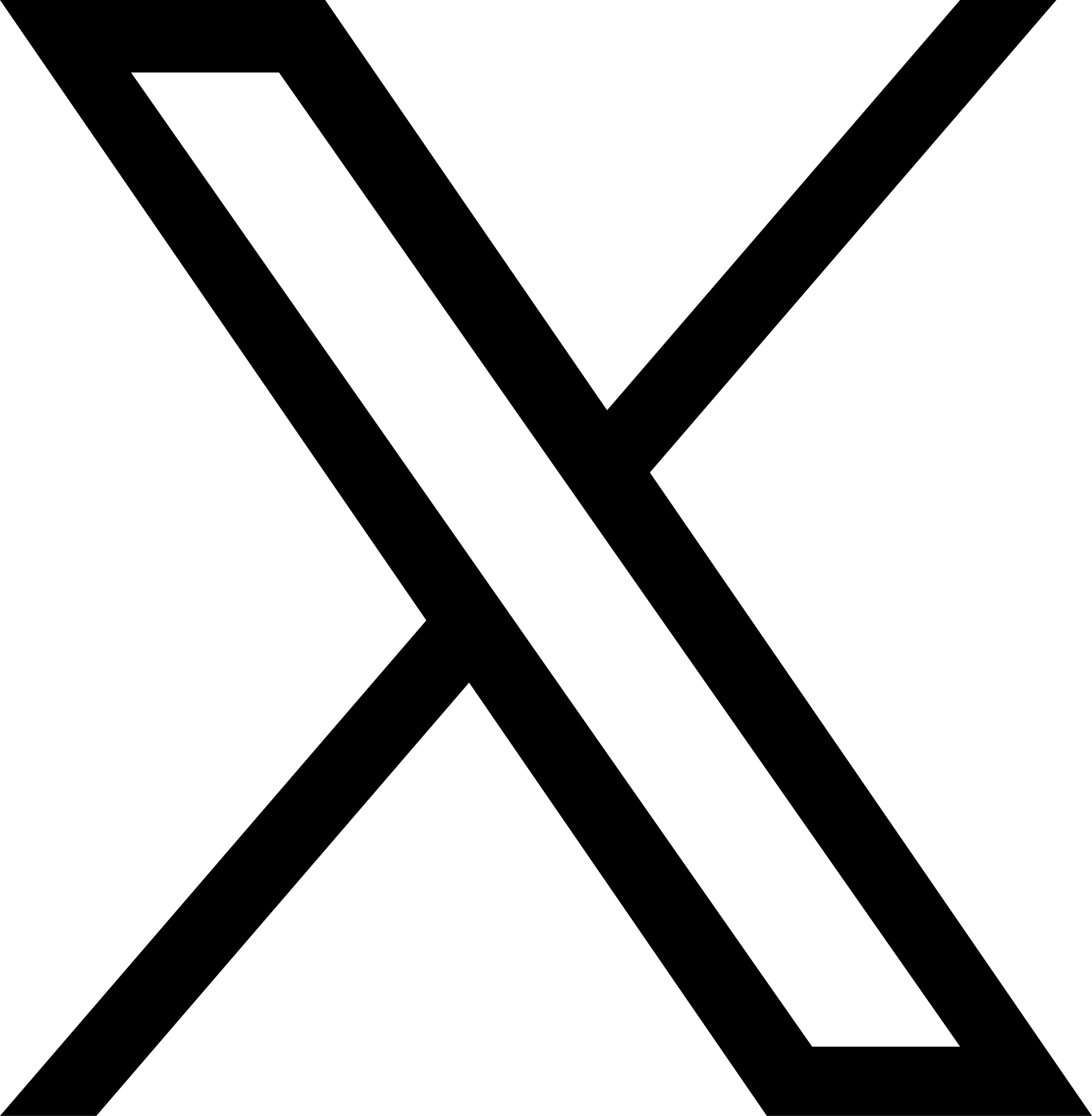本稿では、当社独自調査「観光客の防災対策に関するアンケート調査」の結果を概観しながら、with災害時代の観光客防災と地域行政のあり方を考える。
1.「観光客防災」の潮流
国は、2003年にビジット・ジャパン事業を開始し、2006年の観光立国推進基本法制定を足がかりとして、インバウンド政策を推し進めてきた。その成果は足下の2019年の数値で訪日外国人旅行客数が3,188万人となり、2020年4,000万人の目標には届かないものの、着実にその数を増加してきた。
一方、1990年代以降、我が国では地震災害をはじめとする自然災害が多発し、観光客数の増減率に深刻な影響を及ぼしてきた(図表1)。なかでも、2009年新型インフルエンザ(H1N1)のパンデミックとリーマンショックを上回る規模で、27.8%もの減少率を記録したのが東日本大震災(2011年)によるものであったことは想像に難くないだろう。
東日本大震災時には、首都圏・関東地域の公共交通も寸断され、訪日外国人観光客も被災者となる等甚大な影響があったことから、2014年に地方公共団体向けに、訪日外国人観光客の防災対策の基本方針と、地域防災計画に反映する方策等を示した「訪日外国人旅行者の安全確保のための手引き」を、2016年には観光・宿泊事業者向けに「自然災害発生時の訪日外国人旅行者への初動対応マニュアル策定ガイドライン」を定め、災害多発国にあっても、安全・安心に観光ができる土壌づくりと種まきを始めたのである。・・・(続きは全文紹介をご覧ください。)
2023年7月13日訂正|9頁 注釈「ii」に以下の通り誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
正 251 団体から回答を得た(回収率 40.4%)
誤 250 団体から回答を得た(回収率 40.3%)
テーマ・タグから見つける
テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。