書籍のご案内当社の役職員が執筆した書籍(共著、部分執筆を含む)をご紹介します。
銀行業務検定試験 DXビジネスデザイン 公式テキスト&問題集

- 著者
- 発行年月2024年03月
- 価格定価2,970円(本体2,700円+税10%)
DX支援に必要な知識や能力が身につく本。
取引先の事業を広い視野で捉え、分析によって深く掘り下げることで、真の課題を見つける手法が学べる。支援の糸口や解決策の提案に悩む人に読んでほしい。
銀行業務検定試験「DXビジネスデザイン」の受験対策に必携!
2024年日本はこうなる

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
- 発行年月2023年11月
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
当社のエコノミスト、コンサルタント、研究員の英知を結集した、ビジネスパーソン・学生必読の書。 第1部では、国内外の経済やマーケットの見通しを展望。
第2部では、SX、生成AI、少子化対策、地政学リスク、ポストコロナの人口動向、人権尊重の経営等、今知るべきトレンドを詳説。 第3部では、2024年を理解するための72のテーマを、よりミクロな視点で解説しています。
サステナブル 金融が動く

- 著者
- 発行年月2023年11月
- 価格定価3,190円(本体2,900円+税10%)
カーボンニュートラル社会実現に向けた処方箋
民間金融機関でただ一人COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)に15年以上参加し、日本の排出権ビジネスの草分け的存在である著者が、なぜ金融機関が気候変動問題、グリーンビジネスに動くのかを読み解く。サステナブルに関して、日本には大きなポテンシャルがある。これから金融機関がとるべきアクションとは?
海外取引先管理の実務ハンドブック―激変する世界情勢にいかに対応するか―

- 著者保阪 賀津彦
- 発行年月2023年10月
- 価格定価4,180円(本体3,800円+税10%)
長引くインフレ・円安、高まるカントリーリスクや地政学リスク、気候変動とSDGsへの対応等、海外ビジネスを展開する中で考慮すべき世界情勢は激変している。そうした状況を綿密に分析した上で、最適な調達・販売とその取引先管理をどうするかについて、「地産地消」をキーワードとして実務的に解説する。
地方発 多文化共生のしくみづくり

- 著者編著:徳田 剛 二階堂 裕子 魁生 由美子
部分執筆:加藤 真 - 発行年月2023年10月
- 価格定価3,080円(本体2,800円+税10%)
日本では「多文化共生」の指針のもと外国人住民の受け入れが進められているが、各地方の「現場任せ」になっているのが実情である。さらに、人的資源や組織体制、予算面での不足により、受け入れ態勢が未成熟な地域は少なくない。
本書では、多様な視点から日本の地方部における実情だけでなく、海外の事例も紹介。これから外国人住民がますます暮らしやすい地域にするための課題を考察する。
インパクト評価と価値創造経営―SDGs・ESG時代におけるサステナブルな価値創造の好循環をめざして―

- 著者編著: 塚本 一郎 関 正雄 馬場 英朗
部分執筆:大野 泰資 - 発行年月2023年10月
- 価格定価3,740円(本体3,400円+税10%)
価値創造経営の実現におけるインパクト評価活用の意義・課題・論点について、先行研究や最新事例も踏まえながら実践的に学べる一冊。『インパクト評価と社会イノベーション─SDGs時代における社会的事業の成果をどう可視化するか─』の続編。
レア・アース(2023年版)

- 著者編集:新金属協会、希士類部会
部分執筆:清水 孝太郎、迫田 瞬 - 発行年月2023年09月
- 価格定価5,000円(本体4545円+税10%)
新金属協会から第4版「レア・アース」が刊行されたのは、平成元年(1989年)である。
それから34年の歳月が流れた。この間希土類元素をめぐる環境は大いに変わった。(その後)希土類元素について大きく状況が変わりつつある中、新たに「レア・アース」の新版を出版することとした。本書はこれまでの技術のとりまとめだけでなく、これからの進むべき方向についても述べており、これから新たに希土類元素について取り組んでいこうとされる諸氏に役に立つ内容になっている。
CO2排出量の算出と削減事例ーLCAによる定量化/カーボンニュートラルの推進ー

- 著者編集:技術情報協会
部分執筆:植田 洋行 - 発行年月2023年09月
- 価格定価88,000円(本体80,000円+税10%)
本書では「カーボンニュートラルの動向、政策」「温室効果ガス排出量の算出法とその評価事例」「カーボンプライシングの動向と排出権取引、気候変動開示」「カーボンニュートラルに向けた取り組み例」について、産学官の担当者が解説しています。
税務資料 令和5年度版

- 著者企画編著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 総合相談部
- 発行年月2023年08月25日
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
本書は、毎年の税制改正の内容を織り込みつつ、個人の税金として所得税や相続税など、法人の税金として法人税、グループ法人税制、企業再編税制、連結納税など、また消費税、固定資産税など主だった税金について1冊にまとめた税金全般のコンパクトな解説書です。
外為法ハンドブック2023―犯収法その他関連法令も含めた外為取引への実務的アプローチ―

- 著者企画編著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 国際情報営業部
- 発行年月2023/06/30
- 価格定価5,082円(本体4,620円+税10%)
本書は、第4次FATF対日相互審査結果と同勧告を受け、FATF勧告対応法により改正された外為法、犯収法、国際テロリスト財産凍結法等各法令の概要を掲載・解説しています。
ウィズコロナ時代の都市イノベーション

- 著者編集:公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構
部分執筆:美濃地 研一 - 発行年月2023年06月
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
「企業とイノベーション」「人材」「自治体政策とSDGs」を尼崎市の産業・経済に関わる課題として焦点を当て、多角的に考察。尼崎市の推進する取組みや関西圏における事例の紹介、統計分析、研究報告をまとめている。
一般社団法人 日本産業技術教育学会 実践事例集「テクノロジーとエンジニアリングの教室」第2巻 2022

- 著者編集:一般社団法人 日本産業技術教育学会 実践事例書籍編集委員会
部分執筆:上野 翼 - 発行年月2023年04月
- 価格定価1,760円(本体1,600円+税10%)
本書は、小学校、中学校、高等学校、大学等での教育活動に関する実践事例集です。教員の皆さまに本書籍を手に取っていただくことで、そのまま授業として導入・活用したり、授業の計画・実践・評価・改善のサイクルに役立てていただくことを想定しています。
PMIの実務プロセス

- 著者編著:木俣 貴光
著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング - 発行年月2023年03月
- 価格定価3,960円(本体3,600円+税10%)
M&Aの普及に伴いますます重視されるPMI(買収後の経営統合)。
本書では、対処すべきテーマが多岐にわたり難易度が高いPMIの実務を、専門家が解説する。
まず全体像を示した後、PMIの土台となる「ビジョン」「戦略」「ガバナンス」の統合を説き、さらに「人事領域」「財務・会計領域」「システム」「営業機能」「物流機能」「総務領域」の機能別に統合プロセスと留意点を詳説。
正しく進められているか把握が難しい統合実務を進める上で、折々立ち返るべきガイドラインとして活用できる一冊となっている。
よくわかる事業承継 四訂版

- 著者企画編著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 総合相談部
著者:税理士 蒔田 知子、公認会計士・税理士 小島 浩司 - 発行年月2023/03/13
- 価格定価1,540円(本体1,400円+税10%)
本書は、2019年7月発行「よくわかる事業承継」の改訂版です。
事業承継の現場で発生頻度の高い問題を例示し、その問題を解決するために必要な事柄を項目ごとにわかりやすく解説しています。
人材を活かす 等級制度の基本書

- 著者
- 発行年月2023年02月
- 価格定価3,300円(本体3,000円+税10%)
等級制度の基礎知識、制度改定に取り組む際の論点、制度設計の方法、運用上の留意点を丁寧に解説。
近年の傾向やケーススタディも記載されており、人事担当者必携の1冊です。
①人事制度の「手引き」として活用できる入門書
②等級制度の論点を網羅する専門書
③制度設計・運用の手順やノウハウがまとまっている実務書
として、ご活用ください。
技術トレンドレポート「環境配慮型材料」vol.5

- 著者部分執筆:富田 愛梨
- 発行年月2023年01月
- 価格定価11,000円(本体10,000円+税10%)
近年のSDGsへの取り組みを中心に環境配慮型材料の最新の動向や各企業の取り組みを紹介。
本書ではケミカルリサイクルの最前線として「新CR技術や熱分解ガス化、トレーメーカーの循環型社会への取り組み」他を掲載しています。また、プラスチックリサイクル最新情報として「欧州の取り組み紹介」「食品包装の最前線」を解説。さらに環境配慮型材料のLCA評価、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会の活動報告、マテリアルリサイクル関連の特許出願動向を掲載。
「超スマート社会」への挑戦 日本の光・量子テクノロジー開発最前線

- 著者監修:尾木 蔵人・三菱UFJリサーチ&コンサルティング
- 発行年月2023年01月
- 価格定価1,760円(本体1,600円+税10%)
光・量子が、半導体、スマート製造、スマートモビリティ、セキュリティを変革する。
最先端の光・量子コンピューティングで「超スマート社会」の実現へ!
Society 5.0実現を目指す最前線をわかりやすく紹介。
科学技術イノベーションが拓く、デジタルトランスフォーメーション時代の新たな社会とビジネスのあり方を、すべてのビジネスパーソン・すべての日本人にお届けする1冊。
EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践

- 著者編著:大竹 文雄、内山 融、小林 庸平
- 発行年月2022年12月
- 価格定価3,960円(本体3,600円+税10%)
EBPMの基本的な概念や手法について解説したうえで、米国・英国といった海外の事例や国内における実践例について具体的に解説する。そもそもエビデンスとは何か、EBPMはどのような手順で進めればよいのか、モデルとなるような事例にはどのようなものがあるのか、有益でわかりやすい手がかりを提供する。
脱炭素・脱ロシア時代のEV戦略―EU・中欧・ロシアの現場から―

- 著者編著:池本 修一、田中 宏
部分執筆:土田 陽介 - 発行年月2022年11月
- 価格定価4,620円(本体4,200円+税10%)
世界の脱炭素化をリードしようとする欧州、そこに欧州エネルギーの脱ロシア化の苦悩が始まった。何がその自動車産業集積地・中欧で起きているのか。欧州グリーンディール推進枠でEUがEV化を支援する中、ドイツ主導のグローバルバリューチェインに統合しながらも対抗する在中東欧自動車メーカー。現地日系メーカーのEV化の模索も始まる。
人権尊重の経営 SDGs時代の新たなリスクへの対応

- 著者
- 発行年月2022年11月
- 価格定価2,860円(本体2,600円+税10%)
「ビジネスと人権」の問題が問われるなか、世界主要国中、日本は「人権」への理解が最も遅れている!
サステナビリティの時代に全ての企業が直面する課題にどう取り組むのか?
本書は、この問題への造詣が深い著者が、日本と海外の労働法制の違いにも触れながら、最新事例とともに、いま何が問われているのか、どのような対応が求められているのかをわかりやすく解説するもの。経営幹部はもとより、実務担当者や人事部門、サステナビリティに関心の高いビジネスパーソンにも必携の一冊。
2023年日本はこうなる

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング 編
- 発行年月2022年11月
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームである当社のエコノミスト、コンサルタント、研究員の英知を結集した、ビジネスパーソン・学生必読の書。
第1部では、国内外の経済やマーケットの見通しを展望。
第2部では、SDGs/ESG、サプライチェーンリスク、DXと働き方、人的資本経営、外国人政策等、今知るべきトレンドを詳説。
第3部では、2023年を理解するための73のテーマを、よりミクロな視点で解説しています。
デフレとの20年戦争

- 著者鈴木 明彦
- 発行年月2022年10月
- 価格定価2,750円(本体2,500円+税10%)
2001年3月の月例経済報告に「緩やかなデフレ」であるという分析が載ってから2021年で20年。この長きにわたるデフレとの戦いを著者独自の視点で分析。そして、新型コロナ対応で転換期を迎えたこの戦いは、ウクライナ情勢等による物価上昇でついに終止符を打つのか。戦うべき真の相手を解き明かす。エコノミストが鋭い切り口で語る金融政策と日本経済のこれから。
日韓における外国人労働者の受入れ―制度改革と農業分野の対応─

- 著者編著:深川 博史、水野 敦子
部分執筆:加藤 真 - 発行年月2022/08
- 価格定価5,280円(本体4,800円+税10%)
日韓両国は、少子高齢化などによる労働力不足に直面し、外国人労働者の受入れ拡大に向けて制度改革を進めてきた。しかし、外国人労働者の増加に伴い処遇改善などが課題となっている。特に高齢化の進む農業は外国人労働者への依存を深めており、受入れ継続への切迫感が強い。本書では、これらを日韓共通課題と捉え、その研究成果を収めている。
コロナ後を見据え、在留期間長期化などの見直しが進められるなか、外国人労働者と協働する社会の構築に向けて、課題と克服の過程を隣国の経験から学ぶには、時宜を得た良書である。
カーボンニュートラル燃料最新動向~水素・アンモニア・e-fuel・バイオ燃料~

- 著者部分執筆:石倉 拓史
- 発行年月2022/07
- 価格定価61,600円(本体56,000円+税10%)
EVに移行すれば解決…というほど環境対応は甘くない!様々な観点からCO2削減を考えるべき時代、環境にやさしい燃料とは何があり、実用化への道はどうなっているのか?航空・船舶・自動車・発電各業界側/燃料側の視点それぞれから燃料の環境対応を徹底解説!
国立社会保障・人口問題研究所研究叢書 国際労働移動ネットワークの中の日本 誰が日本を目指すのか

- 著者
- 発行年月2022/04
- 価格定価4,290円(本体3,900円+税10%)
アジア諸国から日本に流入する移民はいまや年間40万人にも及ぶ。彼らはどのような目的と手段で日本にやってきたのか。アジア全域をひとつの巨大な労働市場として包括的に捉え、移住のメカニズムを大規模な調査とデータに基づき精緻に解き明かす意欲作。
第I部は基礎&理論編。移民に関する代表的な理論を紹介し、アジア諸国の移民の実態をデータから詳しく分析。第Ⅱ部は各国編。日本への移民が多いアジア6か国の動向をマクロとミクロの枠組みから詳細に解説。コロナウイルス禍の影響とコロナ後の展望も充実。
バイオマスプラスチック~基礎から最前線まで知りつくす~

- 著者
- 発行年月2022/03
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
プラスチックは、日用品から衣服まで、私たちの暮らしに不可欠なアイテムです。今、その環境問題がクローズアップされています。脱炭素に近づけるためには、プラスチックの原料をできるだけバイオマス由来のものに切り替えることが有効です。
本書では、バイオマスプラスチックの基礎的な知識を専門家が分かり易く紐解いています。そして、未来を拓く技術開発・普及に挑む最前線を紹介しています。一人一人がよく学び、スマートに行動することによって、SDGsへ貢献し、私たちの地球が輝き続けるものと思われます。
カーボンプライシングのフロンティア カーボンニュートラル社会のための制度と技術

- 著者編著:有村 俊秀、杉野 誠、鷲津 明由
部分執筆:吉高 まり - 発行年月2022/03
- 価格定価3,740円(本体3,400円+税10%)
アカデミアと実務の両面に精通する研究者が、カーボンプライシングのフロンティアを示す。文系・理系の枠を超えて、スマート技術を活用した未来社会ビジョンをわかりやすく紹介。工学的な技術開発の成果による社会的波及効果の分析事例についても述べる。
ジョブ型雇用入門

- 著者
- 発行年月2022/03
- 価格定価2,640円(本体2,400円+税10%)
話題の「ジョブ型」について、日本企業で人材マネジメントに携わっている管理職・実務家を対象とした入門書。以前の成果主義ブームの轍を踏んでほしくないという筆者の思いを形にした1冊です。
「ジョブ型雇用」とは、その企業における人材マネジメント全体がジョブ型であって初めて成立するもので、「ジョブ型人事制度」を導入しただけでは、ジョブ型雇用は実現できません。 日本企業において、「ジョブ型」を正しく理解し、「ジョブ型雇用」を検討するために習得しておくべき知識・ノウハウをわかりやすく解説しています。
気仙沼 復興を超えて世界とつながる豊かなローカルへ~自治体とシンクタンクが歩んだ10年~

- 著者編著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング、宮城県気仙沼市
- 発行年月2022/03
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
東日本大震災発災以降、気仙沼市とMURCは、震災復興計画の策定をはじめ、復興からその先の発展を目指してさまざまな場面で取り組みを進めてきました。この取り組みは、大規模災害の被災地域の復旧・復興過程における自治体とシンクタンクとの協働の在り方の1つのモデルとなるものと考えています。
今般、この貴重な両者の歩みを記録として残し広く紹介することで、その経験を後世へ伝えながら、復興を超えて地域の理想の未来を創るにあたり、地域とシンクタンクのそれぞれが果たしうる役割を展望します。
よくわかる現代科学技術史・STS

- 著者編著:塚原 東吾、綾部 広則、藤垣 裕子、柿原 泰、多久和 理実
部分執筆:松岡 夏子 - 発行年月2022/02
- 価格定価3,300円(本体3,000円+税)
本書は、私たちの日常と切っても切り離せない科学技術とどのように付き合い、またその成果やプロセスをいかに判断して、生活の中で対応していくかを考えるための格好のテキスト。
第Ⅰ部では主に戦後から現在までの日本の科学技術史を、大きな事件や課題を手がかりに解説する。そして第Ⅱ部ではSTS(科学技術社会論 Science, Technology and Society ;STS)の立場から、科学技術をどのように考え、対応していけばよいかという諸問題について検討し、解説する。
2022年日本はこうなる

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
- 発行年月2021/11/01
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームである当社のエコノミスト、コンサルタント、研究員の英知を結集した、ビジネスパーソン・学生必読の書。
第1部では、国内外の経済やマーケットの見通しを展望。
第2部では、科学技術イノベーション、脱炭素化と循環経済、サステナブルファイナンス、スマートシティ、コロナ禍と教育格差、ジェンダーギャップ等、今知るべきトレンドを詳説。
第3部では、2022年を理解するための76のテーマを、よりミクロな視点で解説しています。本書の詳細を含めた、2022年の展望をテーマとした情報を、以下のページで順次発信してまいります。
ぜひご参考ください。
「2022年の展望」URL:https://www.murc.jp/kounaru_2022/
日本経済読本 第22版

- 著者大守 隆(編)
部分執筆:中田 一良 - 発行年月2021/11
- 価格定価2,640円(本体2,400円+税10%)
テレワーク、SDGsなどの最新動向もわかりやすく解説!
歴史・制度・事実・理論を組み合わせて経済を理解できるロングセラーテキスト
待望の改訂版 累計39万部!日本経済の歩み、経済政策、財政政策、金融政策、地方経済、日本企業、労働市場、家計、社会保障、国際収支、資源エネルギー、環境問題、世界経済など幅広く解説
進化する人事部 次代に向けた役割・機能変革の視点

- 著者編集:労務行政研究所
部分執筆:小川 昌俊、古川 琢郎、田中 健治 - 発行年月2021/07
- 価格定価2,420円(本体2,200円+税10%)
VUCAに克つ“進化系”人事部の姿とは!?
加速する環境変化の下、人材マネジメントを担う人事部門は新たな岐路に立っています。
組織の課題解決に貢献し、事業の成長を支えていくために。長期にわたるキャリア経験を創造し、人材の定着と成長を促していくために。人事部門の新たな役割・機能変革への要請が高まりつつあります。
事業戦略・人材戦略を展開する上で、これからの人事部門にはどのような価値提供が求められているのか。それを担う人事組織・体制の在り方とは。人事人材に求められるケイパビリティーとは――経験豊富な6社のコンサルタントが、目指すべき“進化像”を明らかにします。
企業買収の実務プロセス(第3版)

- 著者
- 発行年月2021/06
- 価格定価4,400円(本体4,000円+税10%)
ディール遂行上のポイントを時系列で解説するM&A実務書のロングセラー。
「最も使えるM&A実務マニュアル(入門)」をコンセプトに、初版の発刊から10年以上にわたり、多くの企業担当者から高い評価を得ている書籍の最新刊です。第3版では、令和元年会社法改正、税制改正などの制度改正に対応し、加筆・修正を行いました。プロアクティブなM&Aへのニーズを反映し、M&A戦略立案に関する記述を大幅に見直したほか、コロナ禍で問題となったバリュエーション上の論点の追記、株式交付制度にかかるポイント解説、個人情報の取扱い上の留意点や表明保証保険、アーンアウトへの対応の追記など、最新のM&A実務を丁寧に反映しています。
アンダーコロナの移民たち 日本社会の脆弱性があらわれた場所

- 著者編著:鈴木 江理子 部分執筆:加藤 真
- 発行年月2021/05
- 価格定価2,750円(本体2,500円+税10%)
コロナ禍で移民たちが直面している困難は、日本人以上に深刻だ。雇用環境が元々脆弱な上、就職差別にも遭遇している。学びやつながりの困難を抱える人も多い。この状況下でなおも「社会の一員」の可能性を奪い、排除し続けることの意味を問う、画期的な試み。
入門マクロ経済学 第6版

- 著者共著:中谷 巌(一橋大学名誉教授、株式会社不識庵代表取締役)、下井 直毅(多摩大学経営情報学部教授)、塚田 裕昭(三菱UFJリサーチ&コンサルティング主任研究員) 著
- 発行年月2021/03/01
- 価格定価3,080円(本体2,800円+税10%)
マクロ経済学の基礎理論が体系的に学べる。入門テキストの原点に立ち帰ったよりわかりやすい記述へ、大幅改訂。
五訂版 相続・贈与の法律、税金、手続きのポイントQ&A

- 著者著者:税理士 岸本 定雄
企画編集:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 総合相談部 - 発行年月2021/02/22
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
本書では相続・贈与に関して、法律、税金から手続きまでを網羅して、図解や図表による説明や実際の様式を用いて解説しています。
コロナ危機とEUの行方

- 著者編集:EU研究会
共著:土田 陽介 - 発行年月2021/02/15
- 価格定価550円(本体500円+税10%)
2020年に入って突如世界を席巻し始めた新型コロナウイルス感染症は、2020年3月11日にはWHOによってパンデミック宣言され、依然として予断を許さない状況が続いています。このコラムでは、さまざまな立場のEU研究者が、「コロナ危機下のヨーロッパ」がどう動くのか、どこへ向かうのかについて読み解いていきます。
ポスト・オーバーツーリズム 界隈を再生する観光戦略

- 著者編著:阿部 大輔
共著:沼田 壮人 - 発行年月2020/12/25
- 価格定価2,750円(本体2,500円+税10%)
国内外8都市のルポから学ぶ持続的観光戦略
市民生活と訪問客の体験の質に負の影響を及ぼす過度な観光地化=オーバーツーリズム。不満や分断を招く“場所の消費”ではなく、地域社会の居住環境改善につながる持続的なツーリズムを導く方策について、欧州・国内計8都市の状況と住民の動き、政策的対応をルポ的に紹介し、アフターコロナにおける観光政策の可能性を示す。
知財教育研究
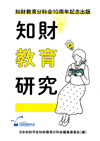
- 著者編集:日本知財学会知財教育分科会編集委員会
部分執筆:上野 翼 - 発行年月2020/12/04
- 価格定価1,870円(本体1,700円+税10%)
本書は日本知財学会知財教育分科会10周年記念出版として、知財教育についての研究成果を取りまとめた研究論文集です。
様々な教科の中で取り扱われる知財教育、これは融合的な教育であることから必然的ですが、一方で根がどこにあるかはっきりしない側面もある知財教育について、「知財教育学」という学問として確立し、教科間をつなぐ横串、よりどころとなる屋台骨を確立したいといった、本分科会メンバーの願いが込められています。
Q&A 持株会社化の考え方と進め方―グループ経営高度化に向けた業務のポイント

- 著者
- 発行年月2020/11/19
- 価格定価2,750円(本体2,500円+税10%)
<なぜ持株会社なのか? 持株会社化の検討や具体化を進めるうえで発生する疑問を解消>
メリット・デメリット、検討のポイント、組織再編の手法、収益基盤の設計、スケジューリングなど、持株会社化の実務において押さえておくべき論点を整理。経営コンサルタントの著者が、実務経験に基づく76のQ&Aでコンパクトに、わかりやすく解説。
独占禁止法改正による純粋持株会社の解禁から20年あまりを経て、複数の事業を営む企業グループで定着してきた持株会社体制について検討・推進を考えている経営者・管理部門職員に最適な一冊。
2021年日本はこうなる

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
- 発行年月2020/11/06
- 価格定価1,760円(本体1,600円+税10%)
三菱UFJフィナンシャル・グループの総合シンクタンクである当社のエコノミスト、コンサルタント、研究員の英知を結集した、ビジネスパーソン・学生必読の書。
第1部では、国内外の経済やマーケットの見通しを展望。
第2部では、AI、SDGs、スマートシティ、グローバルヘルス、行動経済学、気候変動等、今知るべきトレンドを詳説。
第3部では、2021年を理解するための74のテーマを、よりミクロな視点で解説しています。
失敗しない定年延長 「残念なシニア」をつくらないために

- 著者
- 発行年月2020/10/30
- 価格定価880円(本体800円+税10%)
少子化の進展により、日本の生産年齢人口は急激に減少中。さらに、バブル期入社組の大量定年退職が秒読みに入ったことで、労働力不足は深刻さを増すばかり。2020年代において、労働力不足を補うもっとも手近、かつ有用な人材は、世にあふれるシニアたちをおいて他にない。しかし、「日本型雇用」=「会社従属型雇用」にメスを入れずに小手先の定年延長を行えば、「残念なシニア」が大量に生みだされ、企業のみならず日本経済全体の後退をも引き起こす――。
会社の将来を憂う経営者や人事部員、これから定年を迎える会社員、そしてすべてのシニア予備軍へ送る、定年延長を”失敗しない”ための提言書。
基礎から理解するERM―高度化するグローバル規制とリスク管理

- 著者編著:茶野 努、安田 行宏
部分執筆:廉 了 - 発行年月2020/09/18
- 価格定価3,520円(本体3,200円+税10%)
COVID-19のパンデミックに代表されるように、近年多発する世界規模の自然災害や、リーマンショックをはじめとする金融リスク等への対応はいまや現代の企業にとって必須の課題です。
本書は収益、リスク、資本を総合的に管理するERM(統合リスク管理)について、初学者でも学べるようにその考え方から応用まで解説しました。
特に銀行や保険会社における実際の取り組み、金融業界を取り巻く最新の規制についても解説しています。
実践版! グリーンインフラ

- 著者編集:グリーンインフラ研究会、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、日経コンストラクション
部分執筆:遠香 尚史 - 発行年月2020/07/20
- 価格定価4,620円(本体4,200円+税10%)
<国が本気だ、日本は変わる 新しいインフラの現場から77の実践例>
気候変動に伴う自然災害の増加、人口減少・少子高齢化による土地需要の変化や地域経済の停滞、疫病による健康被害--。日本には様々な社会的課題が山積しています。それらの解決に寄与すると期待されているのが、自然が持つ多様な機能を活用したインフラや土地利用計画を指す「グリーンインフラ」です。多くの関係者による普及・事業化のかいあって、今では国も巻き込んだ大きな潮流となっています。51人の第一線の実務家や専門家が実践してきた様々な事例を紹介しながら、知見やノウハウを伝授します。
日本金融の誤解と誤算~通説を疑い検証する~

- 著者編著:伊藤 修 、植林 茂、鵜飼 博史、長田 健
部分執筆:杉山 敏啓 - 発行年月2020/07/15
- 価格定価3,850円(本体3,500円+税10%)
非伝統的金融政策のイノベーション、財政支出拡大は日本経済の停滞を防いだのか、プルーデンス政策、銀行の自己資本比率選択、銀行の店舗数と競争力、金融システムは資本主義中心・銀行中心か、富裕層の資産は不動産かリスク性金融資産か、上場投資信託と出口戦略、終戦前後に市場の断絶はあったのか。金融の通説に挑む画期的試み。
図説 ヨーロッパの証券市場 2020年版

- 著者公益財団法人日本証券経済研究所編
部分執筆:土田 陽介 - 発行年月2020/06/30
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
欧州の証券市場について分かり易く解説するガイドブックとして、「図説 ヨーロッパの証券市場」は1992年以来、「図説 イギリスの証券市場」は1989年以来刊行していますが、今回、両シリーズをあわせた形で「図説 ヨーロッパの証券市場 2020年版」としました。難民問題の深刻化、ポピュリズムの抬頭、ブレグジットの混迷、国際通商問題での軋轢など、より困難で方向性の定めにくい局面にあるEU・欧州諸国の状況の変化を踏まえ、記述内容を抜本的に見直し、再構成しています。これからの欧州証券市場を考えるうえで参考になる一冊です。
「65歳定年延長」の戦略と実務

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング・三菱UFJ信託銀行 編
- 発行年月2020/04/03
- 価格定価4,180円(本体3,800円+税10%)
<生涯現役社会に対応した制度を具体的に提案!>
深刻な人手不足を受け、シニア雇用が変わろうとしている。60歳での定年、再雇用から65歳定年への移行を真剣に検討する企業が増加。制度の変更を前に何を検討すべきか、どのようなメリットがあるのか。コストはどう変化するのか。65歳定年の先にある70歳雇用延長も視野に入れ、注意すべき実務上のポイントを先行事例とともに具体的に解説。企業年金を含めた全体像がわかる。
新版 地域包括ケア サクセスガイド

- 著者監修:埼玉県立大学理事長・日本地域包括ケア学会理事長 田中 滋
編著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング主席研究員 岩名 礼介 - 発行年月2020/02/27
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
地域包括ケアの基本と最新事情がわかる!
高齢化がピークに達し85歳以上人口が1000万人を超える2040年に向け、新たなフェーズに入った地域包括ケアを解説・展望。植木鉢の図が何を意味し、何を目指しているかが120%わかる。確実な未来への解がここにある!
はじめてでもわかる!自治体職員のための観光政策立案必携

- 著者編著:羽田 耕治
部分執筆:原田 昌彦、田中 三文 - 発行年月2020/02/19
- 価格定価2,970円(本体2,700円+税10%)
まちづくりや農林漁業・商業振興など多岐のテーマと関わりあう観光行政。観光に関わる基礎的な用語や市場動向などをまとめた基礎理解編と、観光地マーケティング、観光計画とそのつくり方や外部専門家の生かし方等を解説した実践編が一冊にまとまった、観光行政の必携本。
第14次 業種別審査事典(第10巻)【商社・金融・レンタル・IT(情報通信) 分野】
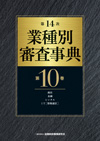
- 著者共著:廉 了 1.商社・金融サービス関連の暗号資産(仮想通貨)交換業の項目を執筆。
新しく出てきた暗号資産(仮想通貨)交換業について、融資を検討する際のポイント(財務内容、環境、規制等)を解説。 - 発行年月2020/02/10
- 価格定価22,000円(本体20,000円+税10%)
東京オリンピック、キャッシュレス決済の普及、インバウンドビジネスの拡大、AI・ロボット産業、シェアリングエコノミー、働き方改革など、数年先の日本の産業界を動かす24の特別テーマ(マクロな経済テーマ)が個々の業種にどのような影響を及ぼすのかを示すことで、中長期事業性評価を肉付け。
イベント・トレンドで伸びる業種、沈む業種 逆引きビジネスガイド2020

- 著者
- 発行年月2020/02/10
- 価格定価2,750円(本体2,500円+税10%)
ポスト2020における日本経済が直面する変化の波を26のテーマで予測しています。どのようなビジネス(業種)が、どのような(ポジティブ/ネガティブ)インパクトを受けるのかを解説しています。
2030年の第4次産業革命 デジタル化する社会とビジネスの未来予測

- 著者尾木 蔵人
- 発行年月2020/01/31
- 価格定価1,760円(本体1,600円+税10%)
スマートダスト、サイバーフィジカルシステム、マスカスタマイズ、MaaS、5G、IoT、AI・・・・・・
最先端のテクノロジー、デジタル化が生み出す第4次産業革命は、すべての社会とビジネスを変革していく。
どんなテクノロジーが登場する?
これからの世界はどう変わるのか?
テクノロジー、注目企業、各国の動向を日本の第一人者が徹底解説!
ヤフーCSO(最高戦略責任者)・慶應義塾大学教授 安宅和人氏、ドイツ ローランド・ベルガー名誉会長 ローランド ベルガー氏ほかのインタビュー収録。
会社を強くする承継の鉄則-経営・所有・家族の承継プランニング

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コーポレートアドバイザリー部[著]
- 発行年月2020/01/09
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
親族間の事業承継を円滑に進めるためのノウハウが満載!
計画の立案から承継後の持続的成長の支援まで、実績豊富なコンサルタントが、「経営・所有・家族」の三つの視点で事業承継・ファミリービジネスのポイントをわかりやすく解説。
後継者の選定・育成、株式承継の方法、目安となるスケジュールなど、実例をもとに気になる論点を網羅。
実務に使える計画表、チェックリスト等のフォーマットも多数掲載。
東海エリアデータブック2020

- 著者中日新聞社・三菱UFJリサーチ&コンサルティング(編)、
共著:田中 三文(第1章②、第2章、第3章、第4章)、内田 俊宏、長尾 尚訓(第1章③「総論」「自動車産業」「航空宇宙産業」「ICT産業」)、平川 彰吾(第1章③「シェアリングサービス」) - 発行年月2019/12/23
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
愛知・岐阜・三重・静岡の各種データと、地域の躍進を示すプロジェクト動向を紹介。東海エリアの特徴と将来展望が、この1冊でわかります。
すごいぞ!はたらく知財ー14歳からの知的財産入門

- 著者共著:内田 朋子、萩原 理史、田口 壮輔、島林 秀行
監修:桑野 雄一郎(高樹町法律事務所) - 発行年月2019/11/26
- 価格定価1,650円(本体1,500円+税10%)
仕事でまいにち、ワクワク!ようこそ知的財産の世界へ!
この本では、著作物、特許、商標、意匠などの知的財産にかかわる11の仕事に焦点をあて、知財を生み出す仕事の奥深さにふれるとともに、そこに生まれるさまざまな権利や、その正しい利用方法をわかりやすく解説します。将来、ものづくりの仕事につきたい中高生から仕事でワクワクしたい社会人まで必須のリテラシーが1冊になった知財入門書の決定版!
海外債権管理の実務ハンドブック

- 著者保阪 賀津彦
- 発行年月2019/11/09
- 価格定価3,740円(本体3,400円+税10%)
支払期日を守らないのが当たり前。倒産も少なくない。商慣習も違う。そんな海外企業の債権管理を具体的に指南。各国・地域別Q&A,海外企業宛て債権管理状況確認シート付。
2020年日本はこうなる

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
- 発行年月2019/11/08
- 価格定価1,760円(本体1,600円+税10%)
三菱UFJフィナンシャル・グループの総合シンクタンクである当社のエコノミスト、コンサルタント、研究員の英知を結集した、ビジネスパーソン・学生必読の書。
第1部では、国内外の経済やマーケットの見通しを展望。
第2部では、AIと脳科学、SDGs、スマートシティ、CASE等、今知るべきトレンドを詳説。
第3部では、2020年を理解するための82のテーマをよりミクロな視点で解説しています。
ドル化とは何か ─日本で米ドルが使われる日

- 著者
- 発行年月2019/10/08
- 価格定価924円(本体840円+税10%)
財政破綻に陥った新興国で進む「ドル化」。自国通貨と共に外国通貨を利用するこの現象を通じて、通貨危機の足音が着実に忍び寄る日本経済の現状を分析する。
政策評価のための因果関係の見つけ方

- 著者エステル・デュフロ(マサチューセッツ工科大学(MIT)経済学科教授) /著
レイチェル・グレナスター(英国国際開発省(DFID)チーフエコノミスト) /著
マイケル・クレーマー(ハーバード大学経済学部教授) /著
小林 庸平(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)経済政策部主任研究員)/監訳・解説
石川 貴之(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)環境・エネルギー部研究員)/訳
井上 領介(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)環境・エネルギー部研究員)/訳
名取 淳(PwCコンサルティング合同会社 People & Organization シニアアソシエイト)/訳 - 発行年月2019/07/25
- 価格定価2,530円(本体2,300円+税10%)
経済学におけるランダム化比較試験のパイオニアであるエステル・デュフロ教授らによる、理論的解説と実践的ノウハウが凝縮。
監訳者である当社小林庸平主任研究員による解説は、難解な部分を直感的でわかりやすい解説で補いながら、近年注目されている「エビデンスに基づく政策形成(EBPM)」にランダム化比較試験をどう活かしていくかを展望。EBPMに関心のある人、経済学の実証研究に関心のある人、必見の1冊です。
e-エストニア デジタル・ガバナンスの最前線

- 著者編著:e-Governance Academy 監訳:三菱UFJリサーチ&コンサルティング
- 発行年月2019/06/10
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
電子行政で世界最先端を走り続けるIT国家の全貌が一目で理解できる公式ビジュアル・ブック。日本初上陸!
バルト海とフィンランド湾に接する人口約130万人の国家、エストニア共和国は、旧ソ連時代に培ったIT関連技術を活用して行政システムをゼロから構築し、現在では行政サービスの99%がオンラインで完結するという世界最高レベルのIT国家へと変貌をとげました。
国外に住む外国人にもインターネット経由で行政サービスを提供するe-レジデンシー制度には1万5000人以上が登録するなど、その先進的なデジタル・ガバナンス(電子行政)への取り組みは、世界中の国々から注目を集めています。
本書は、電子政府やオープンな情報社会の普及を目指して活動しているe-Governance Academy(eGA)が発行しているエストニア政府の公式ガイドブック『e-Estonia: e-Governance in Practice』の全訳で、エストニアにおけるデジタル・ガバナンスの現実を具体的かつ簡潔にまとめたビジュアルブックです。
日本でも、2018年1月に「デジタル・ガバメント実行計画」が策定され、2019年3月には「デジタル手続法案」が閣議決定されるなど、行政の電子化への動きが加速しつつありますが、具体的な施策の計画立案するうえで、本書は数多くのお手本やヒントを私たちに提示してくれます。政府や地方自治体の行政関係者のみならず、デジタル社会における課題の解決やイノベーションの創出に取り組んでいるビジネスパーソンにとっても必読書と言えるでしょう。
「デジタルファースト社会を実現するためのヒントが凝縮された一冊」(平井 卓也 情報通信技術(IT)政策担当内閣府特命担当大臣)
M&A戦略の立案プロセス

- 著者
- 発行年月2019/05/29
- 価格定価2,860円(本体2,600円+税10%)
多くの日本企業にとって、もはやM&Aは日常事となった。統計上、平均すれば1日当り10件以上のM&Aが公表されているが、公表されていないものも含めれば、その数倍ものM&Aが日々実行されているに違いない。買い手としてM&Aを志向する企業は多い。大手企業の中期経営計画には、必ずといっていいほどM&Aに積極的に取り組む姿勢が盛り込まれている。M&Aによる投資予算を掲げる企業も珍しくない。
本書は、企業が買い手としてM&Aをプロアクティブに推進していくための戦略を立案する際のガイドラインとして、企業の経営企画やM&A担当部門の方々に活用していただけることを目指したものである。経営戦略からM&A戦略への落とし込みやM&Aのマネジメントルール、さらに豊富な実例を交えながらM&A戦略の類型にフォーカスを当てている点に最大の特徴がある。
日本経済読本(第21版)

- 著者大守 隆[編] 部分執筆:中田 一良 主任研究員(調査部)「第4章 財政赤字の拡大と再建への取組み」
- 発行年月2019/02/07
- 価格定価2,640円(本体2,400円+税10%)
歴史・制度・事実・理論を組み合わせて経済を理解できるロングセラーテキストの改訂版です。働き方改革、第4次産業革命などの最新動向もわかりやすく解説しています。
日本版ビッグバン以後の金融機関経営: 金融システム改革法の影響と課題

- 著者山沖 義和、茶野 努 編著 部分執筆 廉 了 主席研究員(調査部)「第2章 メガバンク:日本版ビッグバン後の経営動向」
- 発行年月2019/01/25
- 価格定価3,850円(本体3,500円+税10%)
金融システム改革法(いわゆる日本版金融ビッグバン)が施行されて20年。果たして金融面からの日本経済再生は果たされたのでしょうか。
金融ビッグバン以降の規制緩和などの制度改革の効果を検証し、各金融業態に共通する、少子高齢化、ITCの進展、低金利という社会的・経済的環境のなかで今後いかに経営を行っていくべきでしょうか。今後、各金融業態はどのような道を歩んでいくのかに関心がある業界関係者、研究者に最適です。
イベント・トレンドで伸びる業種、沈む業種 逆引きビジネスガイド2019

- 著者
- 発行年月2019/01/23
- 価格定価2,750円(本体2,500円+税10%)
今後5年間に日本経済が直面する24の変化の波が、どのようなビジネス(業種)に、どのような(ポジティブ/ネガティブ)インパクトを及ぼすのかを徹底予測。
■なぜこれから注目されるのか
■関係するビジネスの現状
・主だったプレイヤー、業界
・現在の市場規模
・周辺産業
■中長期的に予想される環境変化
・技術革新
・規制動向
・需給のトレンド
■テーマ・イベントによって影響を受けるビジネス
・新規参入業種、対応を迫られる業種 etc
「逆引き」の“正本”は、半世紀以上にわたり4年に一度改訂を重ねてきた『業種別審査事典』(金融財政事情研究会編)。約1500にのぼる業種ごとに、いわばミクロの視点から沿革、特色、市場規模、需給動向、業況等を分析した『業種別審査事典』に対して本書は、マクロの視点からこれからの日本のビジネスを俯瞰する。
よくわかる オープンイノベーション アクセラレータ入門

- 著者三菱UFJリサーチ&コンサルティング著
執筆者:(共著)
杉原 美智子:はじめに、第3章 実践から得たアクセラレータプログラム運営のポイント、おわりに
石山 泰男:第1章 オープンイノベーションの基礎
附田 一起:第2章 オープンイノベーションの実践
南雲 岳彦:コラム(1) 世界のオープンイノベーション戦略コラム(2) スタートアップ企業が大手自動車部品メーカーと連携して生み出した外観検査の自動化ソリューション...(株)ロビット
渡邉 藤晴:4.1節 第4章 5カ条を実現させる際、企業がぶち当たる壁とその突破方法
渡邉 睦:4.2節、4.5節
辰巳 裕介:4.3節、4.4節
北 洋祐:第5章 産業振興・地方創生に向けたオープンイノベーションの活用
矢野 昌彦:第6章 オープンイノベーションを活用する未来の企業像 - 発行年月2018/12/03
- 価格定価2,420円(本体2,200円+税10%)
革新的な発想や最新のテクノロジーを武器に事業を立ち上げるスタートアップ企業(ベンチャー企業)と大手企業によるオープンイノベーションが今、注目されています。オープンイノベーションの実現のための手法として、「アクセラレータプログラム」が広まりつつあります。
本書は、このアクセラレータプログラムに関して、弊社がこれまで取り組んできた経験を元に、プログラムが本来の成果を発現するための心得やポイントをまとめました。
アクセラレータプログラムでのオープンイノベーションの実践を知るための必読書です。
Q&Aで理解する中堅・中小企業向けM&A
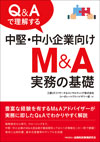
- 著者
- 発行年月2018/10/17
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
M&A戦略策定から実行・PMIまでの実務を幅広く網羅したM&A実務担当者必読の書になります。
大企業だけでなく中堅・中小企業においても、M&Aが経営戦略実行の一手段として不可欠なものになっている現在において、中堅・中小企業の実務担当者(経営陣、実務担当者)が最低限押さえておくべき実務のポイントを当社の豊富な経験を有するM&AアドバイザーがQ&A形式でわかりやすく解説しております。
LIME3 -グローバルスケールのLCAを実現する環境影響評価手法-
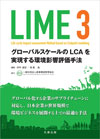
- 著者
- 発行年月2018/08/30
- 価格定価11,000円(本体10,000円+税10%)
本書は、製品やサービスのライフサイクルにおける環境影響を評価する方法であるLIME(Life Cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling)の最新版(LIME3)を解説しています。LIME3はグローバル化する企業のサプライチェーンに対応し、世界各国における被害評価が可能となっています。
世界で活躍する仕事100:10代からの国際協力キャリアナビ

- 著者
- 発行年月2018/07/06
- 価格定価2,420円(本体2,200円+税10%)
当社の研究員・コンサルタント12名及び外部専門家5名が総力をあげて次世代のために執筆。国際協力キャリアを目指す学生、社会人必読の書。
国連、JICA、NGOといった従来の「国際協力」の仕事のみならず、民間企業(メーカー、商社、銀行)や、士師業(弁護士、建築士、看護師、薬剤師)など多方面から国際協力に携わる100の仕事をわかりやすく解説しています。人生100年時代のいま、学び直しや経験の積み重ねを繰り返し、自分の道を探す学生、社会人にとって、指針となる一冊です。
ポートランドの衝撃

- 著者共著 DJむつみ著 部分執筆:上田 義人(政策研究事業本部 研究開発部 副主任研究員)「地方自治体にとって水素社会の到来はどのような意味を持つのか」
- 発行年月2018/04/23
- 価格定価693円(本体630円+税10%)
愛知県議会議員の海外視察レポートを、独特な切り口と写真でつづり“全国初のユニークな議員本”として話題になった「ボルダーの挑戦。-Smart CityにみるAichiの未来-」から6年。
今回、議員らが訪れたのは「全米で最も住みやすい街」にも選ばれたポートランド。
まちづくりに必要なものは何か? これから求められる地方議員とは?
8日間の海外視察をさまざまな視点で描いた、議員による手づくりの報告書籍。
財政破綻後 危機のシナリオ分析

- 著者『財政破綻後 危機のシナリオ分析』小林 慶一郎(編集)
部分執筆『第2章 財政破綻時のトリアージ 第5章 長期の財政再構築』小林 庸平 - 発行年月2018/04/18
- 価格定価2,200円(本体2,000円+税10%)
本書は、「財政危機時のトリアージ」、財政破綻後の「日本銀行の出口戦略」「年金改革」「公的医療と介護」「財政と成長政策」などの重要課題を取り上げ、日本経済・財政の再生への道を探る。
これで納得! 外為マネロン対策Q&A 2018

- 著者監修:三菱UFJ銀行 外為事務部事務管理グループ
編著:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 国際情報営業部 - 発行年月2018/04/01
- 価格定価4,400円(本体4,000円+税10%)
2時間でわかる 図解 貿易新ルール入門

- 著者
- 発行年月2018/02/28
- 価格定価2,530円(本体2,300円+税10%)
本書では、通商政策の動向等を解説しています。まず、世界で自由貿易協定が締結されるようになった背景と世界の各国・地域のFTA・EPAの締結状況について説明しています。 続いて、世界全体での貿易自由化や海外の主要国の通商政策の最近の動向について概観し、日本の通商政策の動向やTPP11や日欧EPAの合意内容についてまとめています。さらには、企業がFTA・EPAを活用する際に必要となる基本的な情報や、EPAを実際に活用している企業の活用事例などについても記述しています。
観光学基礎 観光学入門のための14章

- 著者原田 昌彦(執筆担当:第8章 様々な観光ビジネス―交通運輸業)
- 発行年月2018/02/09
- 価格定価2,300円(本2,093円+税10%)
観光の仕組みや観光に携わる産業の社会的・経済的な役割をわかりやすく解説した観光学の入門書。章ごとに掲載の「本書のポイント」「Extension Study」「Self Check」など、教科書としての使い勝手も好評で、多くの学校で指定教材に採用されているロングセラー商品です。
新訂 介護離職から社員を守る~ワーク・ライフ・バランスの新課題

- 著者佐藤 博樹
矢島 洋子 - 発行年月2018/02/09
- 価格定価1,980円(本体1,800円+税10%)
団塊の世代が75歳以上に到達する2025年には、団塊ジュニア層が親の介護に直面することが予想されます。介護離職による優秀な人材の流出を防止することは、企業にとって今後ますます重要な課題となってきます。本書は、仕事と介護の両立を企業がどうやって支援していくべきか、統計調査や個別事例を基に「事前の情報提供」「制度の見直し」「柔軟な働き方」という視点から解説しています。新訂版では育児・介護休業法、介護保険法の改正を反映するとともに、著者二人による対談を追加し、介護離職と企業の対策をめぐる最近の状況を見渡しています。
コンサルティング業界大研究

- 著者ジョブウェブ コンサルティングファーム研究会
- 発行年月2017/08/31
- 価格定価1,870円(本体1,700円+税10%)
コンサルティング業界入門の定番書。外資から国内注目ファームまで網羅した決定版。
・仕事の基礎知識から実務、業界の行方まで網羅!
・注目ファーム30社超の特徴や強み、最新動向がすぐわかる!
・選考対策から独立後のキャリアまで充実の最新情報!
・各社の採用プロセス(新卒・中途)、育成方針など一覧掲載!
三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、「Chapter3 主要ファームの特徴と戦略」「Chapter5 主要ファームの採用プロセス・トレーニング・配属方法一覧」に掲載されています。
女性営業渉外の育成法 営業の基礎から融資渉外まで

- 著者川井 栄一
植月 彩織 - 発行年月2017/05/19
- 価格定価1,731円(本体1,574円+税10%)
<女性部下の育成を任された上司・先輩・管理職の方>
女性部下の管理育成のご参考事例として、男性部下との接し方の違いや、女性ならではの育成内容、営業渉外に送り出す際の留意点等の確認ツール、さらに、実際の部下とのコミュニケーションにもお役立ていただけます。<営業・渉外業務に携わる女性の方>
お客様へ接する心構えやプロとして業務に臨む姿勢の習得、自己成長のための教材や上司からの指導育成のツールとして、上司と部下ご一緒に、と広くご活用いただければと思います。
プロフェッショナルサービスのビジネスモデル

- 著者高橋 千枝子
- 発行年月2017/05/08
- 価格定価3,960円(本体3,600円+税10%)
特別な資格も生産設備も不要なプロフェッショナルファームは、なぜ政治の重要課題や大企業の経営戦略に関わり、高額な報酬を得られるのでしょうか。コンサルティングファームの比較事例分析より、「知識」を核としたビジネスのマネジメントを探ります。
企業買収の実務プロセス<第2版>

- 著者
- 発行年月2017/03/27
- 価格定価4,180円(本体3,800円+税10%)
本書は、買い手企業の担当者がディールを遂行する上でのポイントを時系列で解説しています。第2版では、平成26年会社法改正や平成29年度税制改正等、M&A実務に影響のある法律・会計・税務面の重要な制度改正をフォローしました。また、M&Aを取り巻く環境変化や裁判例等を踏まえ、最新の実務を反映すべく、ストラクチャリングに関わる部分を中心に、大幅な加筆・修正を行っています。
決定版!グリーンインフラ

- 著者グリーンインフラ研究会、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、日経コンストラクション 編
編集委員(五十音順):加藤 禎久・西田 貴明・西廣 淳・福岡 孝則・吉田 丈人 - 発行年月2017/01/24
- 価格定価3,520円(本体3,200円+税10%)
人口減少や少子高齢化、自然災害のリスク増加、気候変動の進行、地域間競争の激化など、様々な社会問題が顕在化するなか、「グリーンインフラ」は次代を見据えた新しいインフラの概念として期待されています。
産官学の第一線の識者が集まったグリーンインフラ研究会では、これまでグリーンインフラの概念を整理し、各フィールドにおけるグリーンインフラのあり方について議論してきました。
本書では国内外のグリーンインフラの動向、関連事例を紹介するほか、グリーンインフラの将来像やビジネスチャンスについても言及しています。
現代経営戦略の軌跡

- 著者高橋 宏幸・加治 敏雄・丹沢 安治 編著
部分執筆:第4章 日本における外国人労働者政策の検討課題と考察
―「高度人材」の実像と活躍に向けて―
国松 麻季 経済政策部 主任研究員、加藤 真 経済政策部 研究員 - 発行年月2016/12/30
- 価格定価4,730円(本体4,300円+税10%)
グローバル化が進展する中で企業が様々な面で戦略的対応を求められている現在に照らし、経営の各部分領域にかかわる戦略的対応をとりあげている本書のなかで、第4章では外国人活躍推進室のメンバーが外国人労働者の「高度人材」の活躍に向けて検討課題を整理、検討しました。
国松麻季が客員研究員として参加する中央大学経済研究所「現代戦略問題研究会」の研究チームによる研究成果の刊行です。
国際保健医療のキャリアナビ

- 著者日本国際保健医療学会 編
部分執筆:「グローバル・ビジネスを通じた社会貢献を追求」
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 小柴 巌和 - 発行年月2016/12/15
- 価格定価2,970円(本体2,700円+税10%)
国際保健医療の仕事をめざす学生・社会人向けのキャリアガイド.30人のキャリアパスの実例を紹介した上で,仕事に就くための学び方や働き方を詳説.さらに, 学生の質問に編集委員が答える座談会も掲載しています。大学院等への進学や留学,インターンシップや履歴書の書き方等,役立つ情報が満載の本書は,国際保健医療の世界へ飛び立つための必携書です。
銀行激変を読み解く

- 著者廉 了(著)
- 発行年月2016/11/17
- 価格定価946円(本体860円+税10%)
近年、ビジネス環境が激変している銀行業界の最新の動向について、最新の情勢を押さえておきたい銀行マンや、銀行業界を志望する就活生が、理解しやすいように解説した本です。
マイナス金利や日本の金融行政、地銀再編、バーゼル3、フィンテック、世界の金融市場まで、金融関係者なら知ってきたい 銀行を巡るさまざまな環境変化と銀行に与える影響について分析・考察しています。
アベノミクスと税財政改革 — 財政研究 第12巻

- 著者日本財政学会/編
部分執筆 研究論文(2)社会保険料負担は企業の投資を抑制したのか?(小林 庸平・中田 大吾) - 発行年月2016/09/29
- 価格定価5,500円(本体5,000円+税10%)
第72回大会シンポジウム「アベノミクスと税財政改革」,IMFのマイケル・キーン氏による招待講演,4本の特別寄稿論文,4本の投稿論文を収め,財政と財政学の今日的課題を明らかにする。
徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼす 社会的損失40兆円の衝撃

- 著者日本財団 子どもの貧困対策チーム・著
執筆者 日本財団:青柳 光昌、花岡 隼人 / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング:小林 庸平 - 発行年月2016/09/21
- 価格定価858円(本体780円+税10%)
6人に1人とされる子供の貧困を放置すると毎年40兆円の社会的損失が生まれる! データ、当事者インタビュー、国内外の研究紹介、必要な政策提言まで、「他人事」ではない貧困問題の最前線をレポート。
Climate Change Policies and Challenges in Indonesia

- 著者
- 発行年月2016/06/16
- 価格107,09€ 日本価格は書店にてご確認ください。
本書は2章から成り、第1章はインドネシアの気候変動政策とその体制を、緩和・適応・REDD+・JCMといったテーマごとに解説しています。第2章は気候変動に関する具体的な対策・施策の事例を紹介しています。インドネシアの気候変動政策を総論的に理解するのに非常に役立つ1冊です。
新・アジア経済論-中国とアジア・コンセンサスの模索-

- 著者平川 均・石川 幸一・山本 博史・矢野 修一・小原 篤次・小林 尚朗編著
部分執筆: 第6章 アジアにおけるイスラム消費市場 武井 泉 - 発行年月2016/03/15
- 価格定価3,080円(本体2,800円+税10%)
本書は、中国経済が台頭する中で、東アジアのグローバリズムの実態と功罪、そして「ワシントン・コンセンサス」および「北京コンセンサス」の限界を実証的に分析しながら、「アジア・コンセンサス」ともいえる新たな開発協力モデルを提示することを目的としています。中国がこれから構造改革を進めていく中で、東アジアが世界経済の中でどのような位置づけにあるのか、中国の膨張と調整をどのようにとらえればよいのか、どのような地域協力体制を構築すれば共存共栄が実現できるかを考察しています。
持株会社・グループ組織再編・M&Aを活用した事業承継スキーム―後継者・税務・株式評価から考える

- 著者
- 発行年月2016/02/06
- 価格定価4,620円(本体4,200円+税10%)
中小企業から大企業の実務担当者向けに、事業承継対策を講ずる上で必要な知識やノウハウを解説します。具体的には、事業承継の課題や選択肢、プロジェクトの進め方や自社株対策に必要な税務知識を明らかにした上で、持株会社制移行、分社化、持株会、M&A、MBO、IPO、財団法人、海外活用など事業承継スキームを網羅的に解説しています。オーナー企業で事業承継対策を立案する実務担当者や金融機関、会計事務所等で事業承継対策を助言する専門家にも役立つよう、実務的な論点を整理しています。
ISO 14001:2015 要求事項の解説

- 著者吉田 敬史・奥野 麻衣子(共著)
- 発行年月2015/11/20
- 価格定価4,180円(本体3,800円+税10%)
2015年に11年ぶりに改訂となったISO14001規格。本書では、日本代表エキスパートとして改訂作業の国際会議に参加した環境管理システム小委員会委員長と委員が、そこで規定されている要求事項を箇条ごとに具体的に解説しています。新しいISO14001規格の理解には必須となる、定番の1冊です。
ISO 14001:2015 新旧規格の対照と解説

- 著者吉田 敬史・奥野 麻衣子(共著)
- 発行年月2015/11/20
- 価格定価4,510円(本体4,100円+税10%)
2015年に11年ぶりに改訂となったISO14001規格。本書では、日本代表エキスパートとして改訂作業の国際会議に参加した環境管理システム小委員会委員長と委員が、新しいISO14001規格で規定されている要求事項と、改定前のISO14001規格で規定されている要求事項を併記し、比較対照し、解説しています。新しいISO14001規格と改訂前のISO14001規格の違いが一目瞭然です。 新しいISO14001規格への移行に非常に役立つ1冊です。
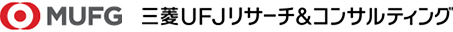
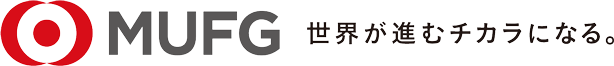



多様な人材を受け入れ,それぞれが能力を発揮し,経営成果として結実させるための戦略がわかる新シリーズ!
「女性(母親)の活躍」と「男性(父親)の子育て」に着目し,企業や家庭・地域における環境の変化を踏まえて,男女の仕事と子育ての両立の形と,企業における支援のあり方を考える。